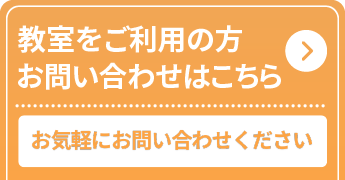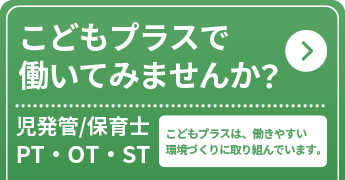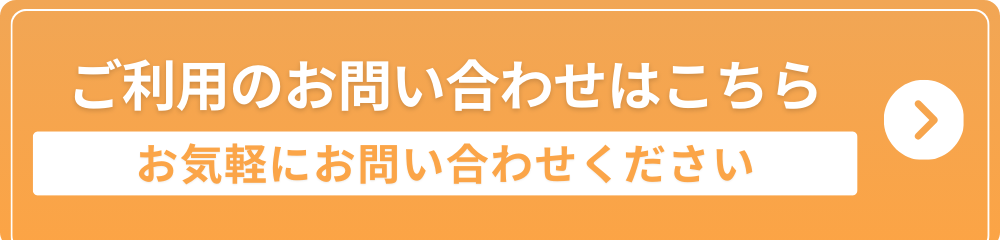お子さんがよくぶつかる・顕くのはなぜ?
~考えられる理由と支援の工夫~
こんにちは。
こどもプラス川越 南大塚教室です🎐
日々の療育の中で、よく壁にぶつかったり、段差のない場所で躓いたりするお子さんと出会うことはありませんか。実はそれにはいくつかの理由があり、適切な支援で改善が期待できることもあります。今回はその原因と関わり方についてご紹介します。
考えられる原因
● 注意欠如・多動症(ADHD)の特性の一つとして、不注意さや多動性により、周囲をよく見ずに動き回ってしまうことがあります。
● 発達性協調運動症(DCD)の特徴として、運動が不器用で、歩く時につま先が地面について躓いてしまうことがあります。
● 股関節や足首に硬さがあると、段差をスムーズに上がるのが難しくなることがあります。
● 足裏の感覚が鈍いと、自分の足がしっかり地面についているか分かりにくくなり、ふ
らつきやすくなります。
● 目の動きが少ないと、障害物や壁などに気づきにくく、ぶつかりやすくなることがあ
ります。
● 靴のサイズが合っていない場合も、躓いたり転びやすくなります。
● 筋肉の緊張のコントロールが難しいと、体の動きがぎこちなくなり、バランスを崩し
やすくなります。
● 自分の体の位置を感じる力(ボディイメージ)が育ちきっていないと、今どこに手足があるのかがわかりづらく、思った通りに体を動かすことが難しくなります。
デメリット
よくぶつかることで、まず怪我のリスクが高まります。それだけでなく、お子さんが運動に自信をなくしてしまったり、運動する機会が減ってしまうことも考えられます。また、遊びの場面で他のお子さんとぶつかることでトラブルが起きやすくなることもあります。
対応策
● トレーニング
1.カップタッチ片足クマ
①クマさんの姿勢からスタートし、片足を上げた状態で進みます。
②並べたカップに手でタッチしながら進みます。
③顎を引いて前を見ることを意識しながら足はなるべく高く上げるようにしましょう。
④2つのコースを並べて競争するなど、徐々に難易度を上げていきましょう。
2.色別ウシガエル
①床に2本のビニールテープを平行に貼り、その間に「手を置く場所」として赤いテープを貼ります。
②ビニールテープの外側には「足を置く場所」として青いテープを貼ります。
③手足 手足の順番でジャンプして進みましょう。
④慣れてきたら、赤と青のテープの位置をランダムに配置し、「赤は手、青は足」というルールを作ってみましょう。楽しみながら、見る力や判断力を育てることができます。
● 環境を調整する
✅ヘッドギアの着用
転びやすいお子さんには、事前にヘッドギアを着用してもらい、転倒時の頭のケガを防ぎましょう。
✅室内の工夫
動き回るプレイルームでは、床にクッションを敷くなどの対策を行ないましょう。また、机の角には角度付きのクッションを付けるなど、転んでもケガをしにくい環境づくりが大切です。
● お子さんへの支援
🔺運動が苦手なことがあるため、自信をなくしやすい傾向があります。できるだけ遊びの
中で運動を楽しんでもらい、運動への興味や好きになる気持ちを育てましょう。
🔺課題や勉強の前など、座っている時間が長くなると集中しづらくなることがあります。
そのような場合、動きの多い遊びで覚醒を促し、集中しやすい状態を作りましょう。
動くのを止めるのが苦手な場合もあるので、動く時間と静かな時間を交互に取り入れま
しょう。
今回は、よく躓いたり、ぶつかってしまうお子さんについてご紹介しました。お子さんの
行動には、さまざまな背景や理由があることをご理解いただき、安心して見守っていただ
けたらと思います。今後も、作業療法士の視点から、お子さん達の発達や関わり方につい
て役立つ情報をお届けしてまいります。ぜひ引き続きご覧いただけますと幸いです。
柳沢運動プログラムの効果
教室で採用している運動遊び
『柳沢運動プログラム』は、
頭からお尻、そして手や足の先まで
全身を余すところなく使った動きで構成されています🤸
たとえ小さな成功でも、
運動を通して経験した確実な進歩は
「自己肯定感」の獲得につながります。
「柳沢運動プログラム」は、
運動の発達を促すだけでなく、
お子さんの「自己肯定感」を高めることにつながる
運動遊びなのです!
今回のお話の、さらに詳しい解説や
柳沢運動プログラムについては
こちらの画像からもご覧いただけます🤗
画像👈